リングの采配において、ルナの視線は常に二重の意味を孕んでいた。華やかなマットの上で繰り広げられる勝敗の裏側には、私的な欲望と公的な戦略が、見事に絡み合っていたのだ。
「イケメンは正義。ファンは正直。それを使って何が悪いの?」
そう言い放つ彼女の言葉には、したたかな計算と揺るぎない自信があった。実際、甘いルックスの若手男子選手をリングに上げれば、会場は歓声に包まれ、グッズは飛ぶように売れる。だが、その選抜基準が見た目だけかといえば、決してそうではなかった。
「どんなに顔が良くても、プロレス魂がなければ、うちのリングには立たせない」
そこには、ルナの確固たる信念があった。彼女がリングに送り出す男たちは、ただ美しくて可愛いだけではない。むしろ、彼らは“負けるために美しい”ことを宿命づけられていた。
「女たちが潰す価値のある、上等な獲物でなければ、意味がないのよ」
ルナが選ぶ“男たち”は、女子レスラーの咆哮と重圧の前に、見事に打ち砕かれることで、観客に新たな快感をもたらした。だからこそ、彼女の演出は唯一無二であり、その手腕には所属選手やスタッフすら一目を置く。
一部では、ルナは“ジャニーさんの女バージョン”と囁かれていた。
「ルナ社長は、まるで“ジャニー女史”だ」
そんな噂も、本人の前ではただの冗談で済まされる。
「あら、プロデュースってそういうものでしょ?」
軽く笑いながらも、どこか本音を隠さないその返しに、誰もが唸らされた。
やがて、ルナの戦略は目に見える形で実を結ぶことになる。
若手のイケメン男子と、圧倒的な強さを誇る女子レスラーが織りなす“逆転構図”は、従来のファン層を一変させた。観客席には、男性だけでなく女性たちの姿が目立つようになり、SNSでは《#潰されたい光くん》がトレンド入りするなど、女子プロの文脈そのものに新たな意味を吹き込んだ。
こうしてルナ・パワーズは、表向きは正統派の女子プロ団体でありながら、その実、“美と欲望と力の交差点”として他団体とは一線を画す独自のポジションを確立していくこととなる。すべては、ルナという女の、美しくも冷徹なプロデュースの手腕によって――。
その“冷徹な美学”は、単なるショービジネスの戦略にとどまらなかった。ルナにとって、プロレスとは舞台であり、選手とは演者であると同時に、生身の欲望を投影する“生ける彫刻”だった。
「リングの上は真実の劇場。誰が誰を愛し、誰が誰を支配するか、すべてが観客の欲望を映し出す鏡よ」
彼女のこの言葉を理解できる者は、そう多くはなかった。だが、理解する者は虜になった。
とりわけ、若手男子レスラーたちは、彼女の目に選ばれることを誇りに思っていた。彼女にとって“潰される価値がある”と認められることは、最大の栄誉だったからだ。
試合の脚本があると知りながら、涙をこらえきれずに倒れる者。
観客の嬌声と拍手に包まれながら、女子レスラーの猛攻に沈む者。
彼らの姿に、ファンたちは“母性”や“征服欲”や“共感”を複雑に重ね合わせ、酔いしれていった。
時にその演出は、「やりすぎだ」と批判された。
「男を商品化している」「屈辱的すぎる」との声も上がった。だがルナは、一歩も引かない。
「誰が誰を欲し、誰が誰に支配されるのか。そこに性別なんて関係ない。欲望は、もっと自由でしょ?」
それがルナの哲学であり、信条だった。
そんな彼女の存在は、いつしかプロレス界において「異端」ではなく、「新潮流」の象徴として語られるようになる。
その風は、他団体にも静かに波及し始めていた。女子レスラーが強く、美しく、そして男たちを“魅せて潰す”という構図は、やがて業界そのものの構造を変えていくことになる。
リング上の悲鳴、汗、張り手の音。
そのすべてが観客の感情を突き動かす装置として機能し、ルナの紡ぐ世界に浸っていく。
だが、彼女の目はもう、次の未来を見据えていた。
さらなる“劇場”の構築。さらなる“獲物”の選抜。
欲望の果てに、彼女が何を見ているのか──それを知る者は、まだいない。
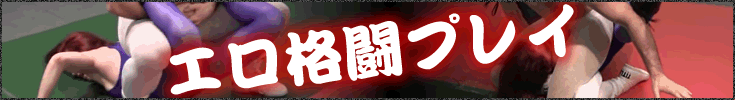
 次回:Luna Mix 北爪妃華01編
次回:Luna Mix 北爪妃華01編